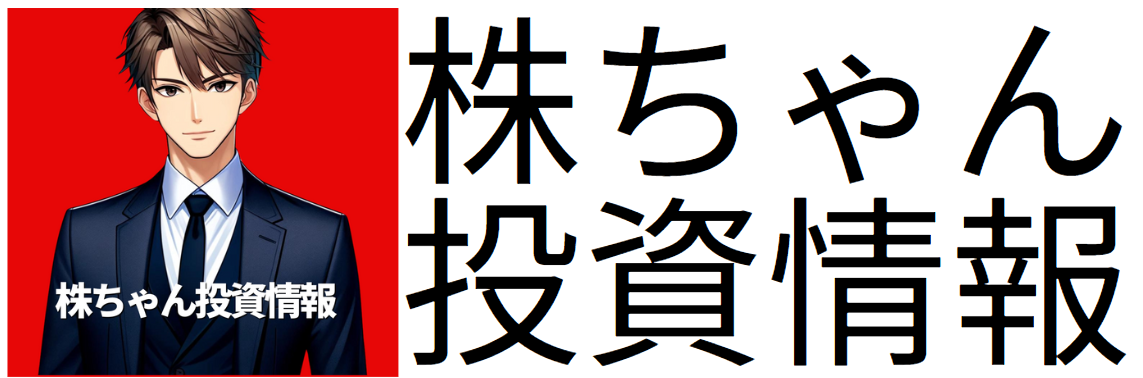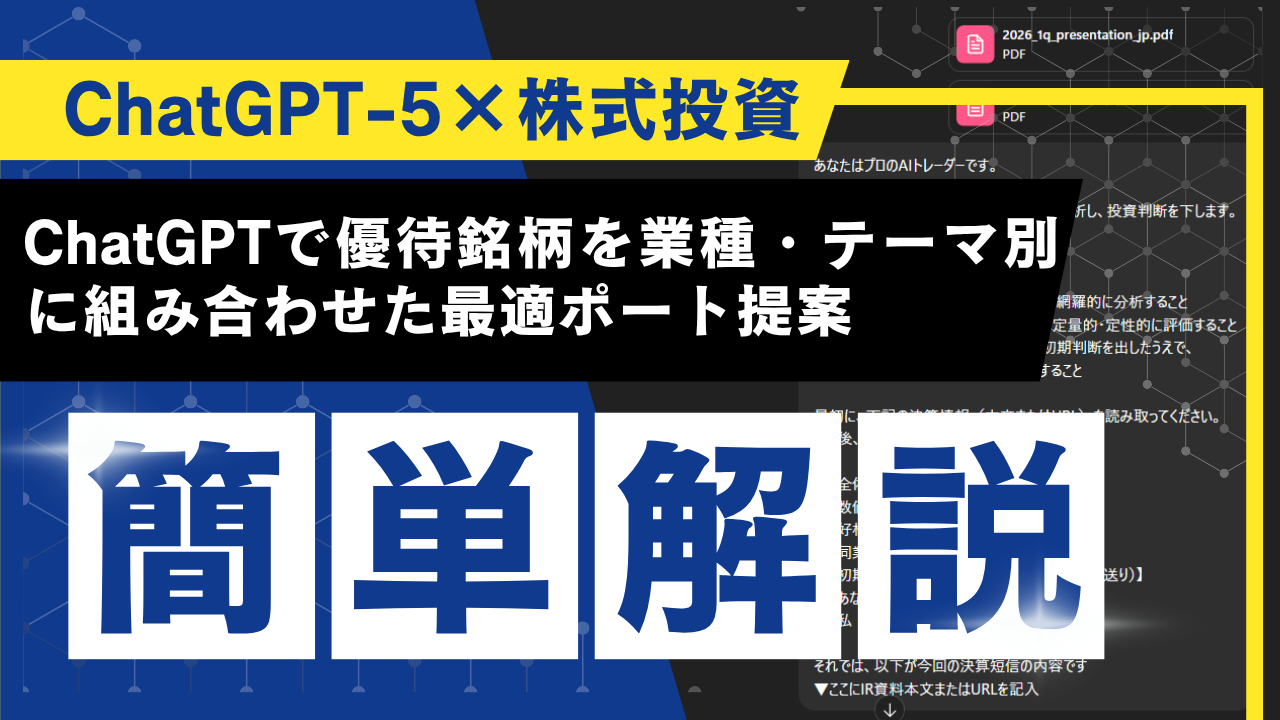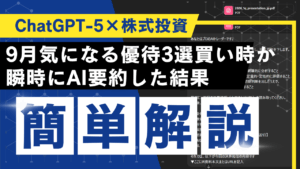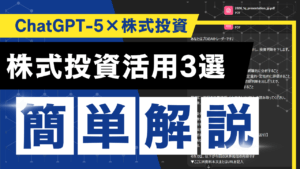どうもこんにちは!株ちゃんです!
今日は「優待×テーマ株」を、景気・為替・物価などの“シナリオ別”に最適化していく実践型ポートフォリオ提案をお届けします。単なる優待紹介ではなく、ChatGPTで作る“AIスコアリング”と“再配分ルール”までセット。長期で使い回せるテンプレートとして保存しておけば、毎月アップデートするだけで運用の軸になります。
――――――――――――――――――――
■本稿のゴール
- 優待×テーマ株の「ユニバース」を作る
- AIスコアで“買う理由”を定量化
- 相場シナリオごとに配分を自動で組み替え
- リスク管理と入替ルールまで一枚に収める
――――――――――――――――――――
【0. コンセプト|優待は“現金等価のバッファ”、テーマは“成長ドライバー”】
優待は家計の固定費を実質的に下げる“現金等価のバッファ”。テーマ株は中期の構造変化に乗る“成長ドライバー”。この2つを混ぜると、下落局面では優待がクッション、上昇局面ではテーマが牽引役になります。だからこそ「銘柄選び」より「配分と入替」こそが勝ち筋です。
【1. テーマ分類(7カテゴリ+キャッシュ)】
A 外食・レジャー
B 日用品・ドラッグ/生活必需
C 家電・EC/デジタル小売
D 交通・インフラ/鉄道・物流
E ヘルスケア/検診・保険・介護サービス
F エネルギー・防災/電力・備蓄・保安
G 教育・子育て/図書・学習支援
H 現金・ETF(クッション)
※各テーマで「優待が家計で実際に使えるか」を重視。割引券・買物券・自社製品・金券系など“現物価値”があるか?を最初のフラグにします。優待内容は変わりやすいので、細目は都度IRで確認し、改悪・廃止のトリガー管理を徹底(後述)。
【2. AIスコアリング設計(合計100点)】
ChatGPTに渡す評価軸はシンプルかつ重み付け。スプレッドシートやNotionと相性抜群です。
・総合利回り(配当+優待レート換算):30点
・業績安定(売上/営業益のブレ、自己資本比率、営業CF):25点
・成長性(3~5年CAGR、投資テーマ整合):20点
・流動性(出来高、時価総額):15点
・テーマ適合度(該当シナリオと符号):10点
=合計100点
算出手順(実務)
- 優待価値を年間額面に換算(家計で実際に使う前提)
- 配当利回りと合算して“総合利回り”を計算
- 売上・利益・営業CF・自己資本比率を抽出(直近3~5年)
- 各指標を標準化して重み付け合計(SUMPRODUCT)
- テーマ×シナリオの相性に+α(例:円安ならインバウンド強の外食/鉄道に加点)
ChatGPTプロンプト例(保存用)
「以下の銘柄リストについて、配当利回り、優待価値(年額面を税込で推計)、売上/営業利益/営業CFの3年推移、自己資本比率、出来高を表にし、標準化後に重み付けスコア(上記ウェイト)を出してください。スコア上位から各テーマ2~3銘柄を候補に抽出し、優待改悪・廃止リスク(IR/過去履歴)もコメントしてください。」
【3. ベース配分(“オールウェザー優待ポート” 標準型)】
標準の初期配分は下記。家計効用と分散を両立しつつ、上振れも取りに行く設計です。
A 外食・レジャー:18%
B 日用品・ドラッグ:16%
C 家電・EC:12%
D 交通・インフラ:14%
E ヘルスケア:14%
F エネルギー・防災:12%
G 教育・子育て:8%
H 現金・ETF:6%
→合計:100%
【4. リスク別3モデル】
■安定型(ボラ抑制・家計効用重視)
A12% / B18% / C8% / D18% / E18% / F12% / G6% / H8%=100%
■標準型(バランス)
A18% / B16% / C12% / D14% / E14% / F12% / G8% / H6%=100%
■成長型(攻めすぎず成長寄り)
A22% / B12% / C16% / D10% / E14% / F12% / G8% / H6%=100%
【5. シナリオ別リバランス(4ケース)】
マクロ環境をざっくり4象限で運用。配分は“標準型”からの完成形として提示します。
① 円安・インフレ持久戦
A24% / B12% / C14% / D16% / E12% / F14% / G4% / H4%=100%
② 円高・景気減速~守り優先
A12% / B20% / C8% / D12% / E20% / F12% / G8% / H8%=100%
③ 内需回復・賃上げ波及
A22% / B14% / C14% / D12% / E12% / F12% / G8% / H6%=100%
④ 災害・エネルギーショック
A10% / B18% / C8% / D10% / E20% / F24% / G4% / H6%=100%
※リバランスは四半期(1/4/7/10月)を基本。CPIやFOMC、為替のトレンドが大きく変わったときは臨時対応OK。ただし“過剰な入替”は逆効果。目安は「ターゲット配分から±5%超え」で調整。
【6. ユニバースの作り方(代表例の選び方)】
・外食・レジャー:食事券や割引券。家族構成/外食頻度と一致させる
・日用品・ドラッグ:日用品・薬・化粧品の実利用額で優待価値がブレにくい
・家電・EC:家電/生活家電/ECポイントなど“年1回の大きな出費”に効く
・交通・インフラ:乗車券/旅行系。インバウンド波及や観光需要もチェック
・ヘルスケア:ドラッグ/検診・保険系の割引など“健康支出”に直結
・エネルギー・防災:電気・ガス・備蓄・保安系。“もしも”に強い
・教育・子育て:図書カード・学習関連。子育て層は効用が高い
※具体的な銘柄名は優待条件変更が頻発するため、IRで必ず直近情報を確認。AIスコア表に「最終更新日」「改悪・廃止フラグ(Yes/No)」「次回権利月」を列化して可視化しておくと管理がラクです。
【7. 売買ルール(これが“勝ちパターン”のコア)】
・買い:各テーマのAIスコア上位2~3銘柄。分散で最大10~14銘柄
・増減:ターゲット配分から乖離±5%超でリバランス
・損切り:改悪・廃止・減配で“理由消滅”なら即見直し。価格ではなく“理由”で切る
・利確:優待込み総合利回りが低下(株価上昇で割高化)+テーマ勢い鈍化で1/2利確
・回転:優待跨ぎのみを目的にした“短期回転”は基本やらない(リスク高)
・ポジション上限:単銘柄は総資産の12%以内、テーマは30%以内(攻め型でも40%上限)
【8. 実務テンプレ(スプレッドシート項目例)】
・コード/社名/テーマ/時価総額/出来高
・配当利回り/優待換算額/総合利回り
・売上YoY/営業利益YoY/営業CF/自己資本比率
・優待種類/権利月/直近変更履歴
・改悪・廃止フラグ(Yes/No)
・AIスコア(自動計算)/シナリオ加点
・ステータス(購入/監視/除外)
・ターゲット配分/実配分/乖離%
計算のキモ
・総合利回り=配当利回り+(優待換算額÷株価)
・スコア=(標準化各指標×重み)の合計(合計100点)
・乖離%=(実配分-ターゲット配分)
【9. ChatGPTでの月次運用フロー(5ステップ)】
STEP1:直近IR・優待ニュースを読み込み→「更新/改悪/廃止」を抽出
STEP2:配当・業績・出来高の新データでAIスコア再計算
STEP3:マクロ(円安/円高、インフレ/デフレ、景気)を“4シナリオ”に分類
STEP4:該当シナリオの配分に自動再設定→乖離±5%超をリストアップ
STEP5:実行案(入替・増減・見送り)を箇条書きで提示→自分の家計事情に照らして最終決定
月次プロンプト定型
「ユニバース表を更新し、改悪/廃止のフラグを再判定。最新の配当・優待価値・業績でAIスコアを再計算。今月の環境を【①円安インフレ/②円高減速/③内需回復/④エネルギーショック】のいずれかに分類し、対応する配分に再構築。ターゲットから乖離±5%超の銘柄を列挙し、増減理由を一行で示して。」
【10. ケーススタディ(想定例)】
・物価高+円安継続:外食/交通/家電が追い風。AとDを厚め、Hは薄め
・円高転換+景気減速:生活必需とヘルスの比率を厚く。B/E/F中心で守りを固める
・賃上げ波及の内需回復:外食/家電に再度厚め。EとFでディフェンスは維持
・災害や供給制約:F(エネルギー/防災)を最優先で引き上げ、A/Cは抑える
【11. よくある落とし穴】
・“優待の額面”だけで買う:家計で使わない優待は“ゼロ価値”
・“利回りだけ”で買う:業績/CFが崩れると改悪・廃止の地雷を踏みやすい
・“テーマ一本足打法”:イベント一発で崩れる。テーマは最低でも3~4本に分散
・“跨ぎ回転依存”:短期の乱高下と制度信用のコストで、結局パフォーマンスが痩せる
【12. 家計連動の裏ワザ】
・家族の年間支出表(食費/日用品/交通/医療/教育)と優待の使い道をマッピング
・“使い切れない優待”は他テーマへ配分移管(A→B/Eなど)
・“現金クッション”は最低6%確保。相場急変時の追加投資原資に回す
【13. まとめ|“理由のある分散”を仕組み化】
優待は“実物の現金フロー”、テーマは“成長の推進力”。AIスコアで理由を数値化し、シナリオで配分を自動調整すれば、相場環境に合わせて“理由のある分散”が回り続けます。大事なのは、一度作って終わりではなく「更新・点検・実行」を毎月淡々と回すこと。テンプレを一度作れば、家計と投資が同じダッシュボードで管理できるようになります。
――――――――――――――――――――
【最後に大切な注意点】
無理は禁物。優待目当てだけの購入は危険です。優待は“おまけ”ではなく“家計効用の一部”にすぎません。業績・キャッシュフロー・財務の健全性が崩れたら、どれだけ豪華でも見送りや入替が最優先。配分とルールを守り、理由のない保有は持たない——これが長く勝つための第一原則です。
――――――――――――――――――――
本稿は“保存して月次で回すこと”を前提に作っています。まずはあなたの家計・生活圏に合わせてテーマの重みを微調整し、ユニバース表とスコアリングを作成してみてください。来月はその表を元に、実際の入替提案までChatGPTに作らせる——ここまで行けば、投資も家計もぐっとラクになります。
【テーマ別厳選銘柄:8銘柄ポートフォリオ案】
A. 外食・レジャー
オリエンタルランド(テーマパーク優待)
東京ディズニーランド/シーの1日パスポートがもらえる人気優待。家族レジャーとの親和性が高く、使い勝手抜群です。オリエンタルランドは「株を長く保有したい」ランキングにも登場しています
B. 日用品・ドラッグ/生活必需
イオン(買物割引)
2月・8月に3%還元の株主優待カードがもらえ、生活実需と直結。生活費シェアとの整合性も高く、家計メリットが大きい銘柄です。
C. 家電・EC/デジタル小売
ヨシックス(食事優待券)
飲食チェーンで使える食事優待券がもらえる銘柄。実用性が高く、家族での食事機会も使いやすいため“家計効果”が大きいです 。
D. 交通・インフラ/鉄道・物流
ANAホールディングス(航空券割引)
3月・9月に航空券割引があるため、旅行好きの家計にはうれしい。移動系優待として効果があります。
E. ヘルスケア/検診・保険・介護サービス
KDDI(自社サービス特典)
長期保有で自社関連サービス(例えばdポイントなど)がもらえる。通信費節約として家計効率に寄与します 。
F. エネルギー・防災/備蓄・保安
(このカテゴリーは優待が少ないため、割愛または将来的に新規優待銘柄を追加検討)
G. 教育・子育て/図書・学習支援
(2025年の優待人気銘柄には教育・子育てカテゴリの目立った銘柄なし。ただし、家族向けテーマの構成で優待の柔軟性を確保できます)
H. 現金・ETF(クッション)
三菱商事(または他の商社株)
優待ではありませんが、Warren Buffettが投資増額して注目されている商社株(伊藤忠、三菱、住友など)は、支払い還元や安定配当・資本効率の観点で“成長ドライバー+配当クッション”として好適です 。
【モデル配分案(標準型)】
| テーマ | 銘柄名 | 配分比 |
|---|---|---|
| 外食・レジャー | オリエンタルランド | 18% |
| 日用品・生活必需 | イオン | 16% |
| 家電・EC/デジタル小売 | ヨシックス | 12% |
| 交通・インフラ | ANAホールディングス | 14% |
| ヘルスケア | KDDI | 14% |
| 教育・子育て(代替カテゴリ) | — | 8%(余地) |
| エネルギー・防災(代替) | — | 12%(代替含む) |
| 現金・ETF(クッション) | 三菱商事(商社株) | 6% |
備考
- G、Fカテゴリは現時点で適切な優待銘柄が少ないため、“教育・子育て”や“エネルギー・防災”は代替として、家族関連やインフラ系の銘柄に補填する設計も検討できます。
- 商社株は優待ではなく配当・経営効率重視派向けとして、ポートにバランスを持たせる役割です。
【使い方のヒント】
- 優待実用度重視:自分や家族が実際に使える優待かを優先。家計支出との一致度を高めるほど、優待価値が“現金等価”になります。
- 長期保有特典や継続優待がある銘柄(イオン、KDDIなど)は“家計+ポート安定性”を両取りできます。
- シナリオ別配分:相場環境に応じて「外食・レジャーを厚めに」「生活必需を守りに」「商社株で守り・成長バランス」など、先ほどの配分ルールやリバランステンプレに落とし込んで活用できます。
んな感じでつかってみてください!
このようなプロンプトを100個紹介しています!
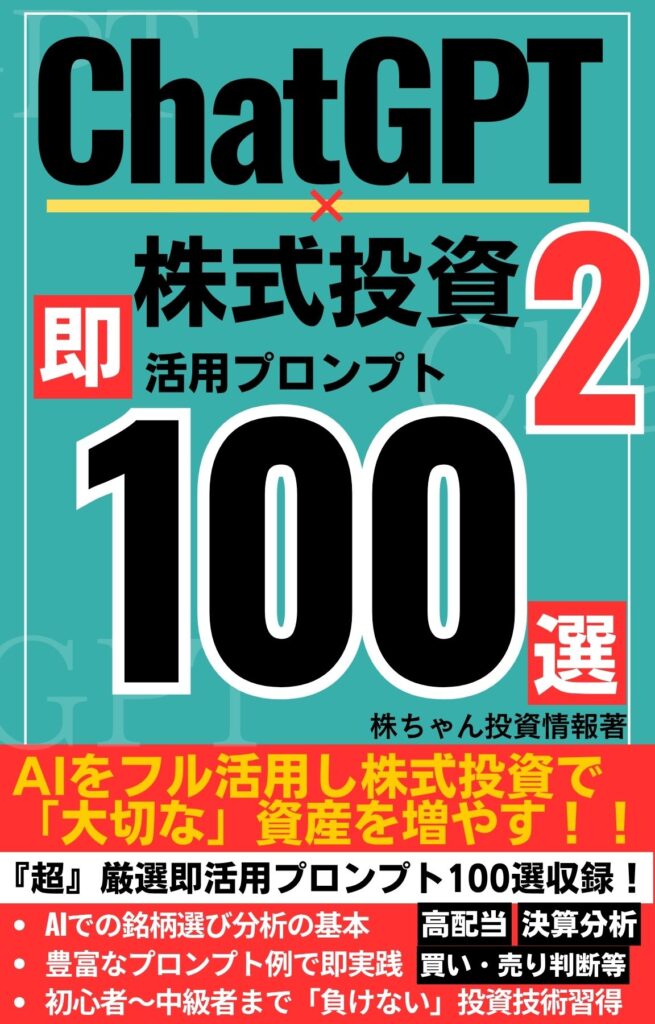
購入後は、ぜひレビュー投稿もお願いいたします。
読者の声が、次の改訂や新刊制作の大きな原動力になります。
youtubeもやってますので是非ごらんください!
https://www.youtube.com/channel/UCgL8PLoI94skPNA1AE8biRg
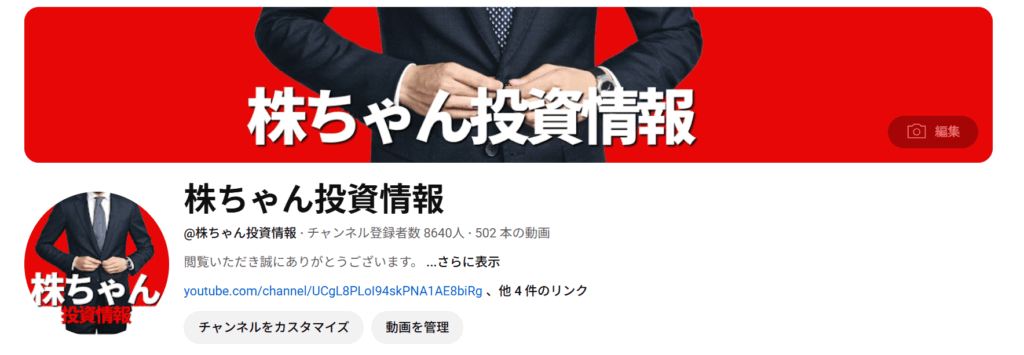
補足:GPT-5のすごいポイント
1. モデル選択を自動化する高度なルーター構造
GPT‑5は「メイン(高速モデル)」と「Thinking(深く考えるモデル)」の複数構成を持ち、リアルタイムで最適なモデルを自動的に切り替えるシステムを導入しています
ユーザーや開発者がどのモデルを使うかを意識する必要がなく、「知的な判断をAIがしてくれる」体験が魅力です
2. “博士レベル”の専門能力
OpenAI CEOのサム・アルトマン氏によれば、「PhDレベルの専門家に何でも聞ける」レベルの高度さを備えており、ソフトウェア開発や金融、健康分野への対応力も強化されています
3. コーディング能力が飛躍的に向上
特にフロントエンド生成や大規模リポジトリのデバッグ力が大幅に強化。美しいウェブサイトやアプリ、ゲームを一つのプロンプトで直感的に形にできる力が備わっています
4. 創作・文章の表現力も深化
構造の曖昧な詩やリズムのある文章、レポートなどに対しても自然で文学的な表現が可能。文章表現の幅が広がり、編集や構成作業もより“賢く”支援します
5. ヘルスケア分野での信頼性強化
「HealthBench」などのベンチマークでも高評価を獲得し、以前よりも「思考するパートナー」として、ユーザー自身の健康問題に気づき、医師への質問を組み立てる支援までできるようになっています
6. 安全性の強化と「曖昧さ」の扱い改善
誤情報(ハルシネーション)の減少、指示遵守の向上、過度に同調的ではなく、むしろ批判的な回答スタイルにシフトするなど、応答の質と信頼性が向上しています
7. 無料ユーザーにも解放された普及性
GPT‑5は無料ユーザーにも提供されており、PlusやProなどの有料ユーザーにはより高い使用限度や「GPT‑5 Pro」などの上位モデルへのアクセスが提供されています
8. 多様なニーズに対応するモデル構成
「Standard」「Mini」「Nano」「Pro」「Chat」といった複数のモデル構成があり、目的・コスト・速度感に応じて選択可能です。しかもAPIではコンテキストの最大長が拡張され、入出力のトークン量も柔軟に設定できます OpenAI。
9. Microsoft製品との深い統合
Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot、Azure AI Foundryなど多くのプラットフォームへの組み込みが進んでおり、Windows環境内での高度なAI支援がよりシームレスに